「稼ぎ」と「仕事」について考える
ものづくりの 「もの」 とは何か?
「断捨離」「ミニマリスト」など昨今、耳にするようになった言葉は、モノがあふれ返った現代社会を反映しています。一方で、針供養、筆供養、鏡供養などの行事はモノではなく、何かが宿る「もの」として先人が向き合ってきた証と言えます。
「もの」とは何だろうか。「もの」に宿っている何かとは? 私たちは、いつから「もの」を「モノ」として扱うようになったのか。そこには本来、意味の異なる言葉である「稼ぎ」と「仕事」をないまぜにして使ってしまう、私たち自身の姿や社会のありようも見て取れます。なぜ、そうなってしまうのか。なぜ、そうなってしまったのか。内山節さんとじっくり考えてみたいと思っています。(由井)
内山さんからレジュメが届きましたので添付しておきます。当日の対談は、レジュメを手掛かりにトークセッションの流れに任せて進めていく予定です。
「もの」の哲学を考える
2025/4/5 川崎・梶ヶ谷
1、はじめに
―「もの」はどこから生まれたのか
2、西洋思想と「もの」についての発想
―基本的な物質の組み合わせからつくられたという考え方
―初期のギリシア哲学では火、土、水からすべてのものはつくられたなど
―おおもとの物質は原子と考えた原子論派・・・たとえばデモクリトスなどの発想
―いまでも科学はおおもとの物質を探している・・・素粒子、クオーク
3、インドに生まれた大乗仏教はこの問題をどう考えたか
―すべてのものは関係からつくられているという視点
―我をつくりだしているものは全宇宙的関係とした龍樹の空の思想
―人間の奥にも全宇宙的関係によってつくられた深層の意識=阿頼耶識があるとした世親
の唯識思想
―個々の実態と思われているものは関係からつくられた現象にすぎないとする視点
4、日本の伝統思想と自然信仰について
―自然(しぜん)と自然(じねん)
―自然(じねん)の関係が自然(しぜん)をつくりだしているという視点
―自然(じねん)の関係に清浄な世界=神、仏の世界を見る
―人間は自然(じねん)の関係だけで生きていないがゆえにさまざまな問題を起こすだけで
はなく、我欲を抱くことによって自分自身も苦悩するという視点
―日本の自然(しぜん)信仰もまた関係本質論
―ゆえに民衆のなかに大乗仏教が浸透した
5、日本の「もの」づくりの精神について
―たとえば家を建てるとすると
・・・自然との関係からつくられてくるさまざまな素材
・・・建て主との関係、多様な職人との関係などから家という「もの」が生まれてくる
―自然との関係を見る、人々との関係を見る
―清浄な関係を実現させるための技
6、「もの」とは物質のことなのか
―関係から「もの」が生まれるのなら、「もの」は物質、非物質を問わない
―関係から生まれた物語、この世界のゆがんだ関係から生まれた物の怪
7、西洋思想と物質本質論、東洋に生まれた関係本質論
―その違いを踏まえながら
8、まとめに代えて
―関係論の視点から「もの」を考える

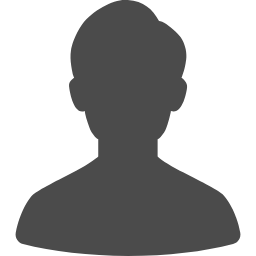





 「幻燈がたり」岡谷編 8.6Sat、8.7Sun
「幻燈がたり」岡谷編 8.6Sat、8.7Sun 3
3 ものがたりをめぐる物語
ものがたりをめぐる物語
岡谷市
2025/04/13
その日の60分弱のお話は、人は本来全宇宙的なものを内包しているとした大乗仏教を大成された1600年以上前の龍樹と世親の姿、東洋思想に本質を見出そうとする230年前のヨーロッパの哲学者の姿、「じねん」と「しぜん」に横たわる日本独自の自然観のずれを生んだ150年前の明治の知識人の姿、世の中を虚無的に見始めている現代の人の姿など、数々の登場人物が現れては消える映像風景のように感じながら聞いておりました。
すこしオーバーかもしれませんが、自分を構成するジグソーパズルのピースの一部が間違ってハメられていたことを気づかせ、もしくは新たなピースが見つかったような感覚もあり、自分の中身を見直すことができた貴重なお話だったと思っております。
印象に残った要点は、勝ち負けを作らないとする「寄合い」という共同体としての考え方と、最近増えつつある『宗教ではない信仰を取り戻したい』と考えている人々の存在についてでした。前者においては目上の方々との付き合いの中で感じていた感覚でして、非効率的で、あまり意味のないものと考えていた部分でして「禍根を残さないためのシステム」という視点は、すぐに答えを求めすぎている現代の流れの早さを強く感じ、後者については、どんなにノウハウを培っても、最終的には「自分が他者(社会)と何がしたいのか」は自分の中で悩み考える必要があったことを示唆されたように感じました。
そして、最後に『「本当に大切なことはなにか」を考える出発点(にいる)』と述べられた時に、自分もいつか某かの達観があるのかなと思っていましたが、そうではなく、きっと最後まで悩み、喜び、考え、あるいは忘れ、そしてまた教えてもらっていくのだなあと理解し穏やかな心持ちになりました。
またもっと色々なお話を聞きたいと感じました。ありがとうございました。